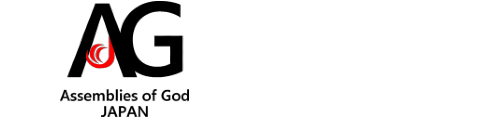《福音》恵みのおとずれ 1996年9月号
それは、一人の御婦人の突然の来訪から始まった。葬儀の依頼だった。話を伺うと、御主人の父娘で何んと百六才の御方なのだそうだ。お国は隣国、韓国の方で、九三才の時に苫小牧在住の御長男のもとへ身を寄せられた。
お国で七十才の時に信じ、熱心に教会へお通いになっていたとのことである。日本の息子たちから送られてくる小遣(こづかい)も、自分のためには使わずに教会のためにと献金していた。こちらに来てからは、言葉の問題もあり、教会へは行けなかったが、日々聖書に親しまれ、好きな珈琲を一杯飲む時も祈りの姿勢をとったと言う。
そんな父親が、今日明日とも知れぬようになったので何とかキリスト教式で旅立たせてあげたい、そんな気持でたずねて来られたと言うのである。
僕にとっては、まさに、「突然、天から」 であった。人の一生で百六才の人に接すると言うこと自体が稀(まれ)なことなのに、その人の人生の幕引きをさせて頂くと言うことなど、僕の人生に二度とは無いことだと思った。
牧師は死人のところに行くのが仕事ではない。生きているうちにお顔を拝見し、お祈りをしたいと思い、次の日の午前中にお宅を訪ねた。奥の間に横になっておられた。白衣の国の長老にふさわしいお顔であった。御老人は日本語を解さず、 僕は韓国語はダメ。でも聖歌六〇七番を大声で歌い、詩篇二三を朗読し、手を握ってお祈りをした。
人間の五感のうち最後まで残るのは聴覚だそうなので僕は御老人の耳元(みみもと)に唇を寄せて祈った。すると、ご老人は私の手を力強く何回も何回も強く、力をこめて握りかえして下さった。うれしかった。言葉は通じなくても祈りは通じる。祈りは万国共通の魂の感動なのだ。祈り終っても僕の手は御老人に握られたままだった。翌朝は主の復活の日曜日。朝食をとっていると電話が鳴った。御老人の召天を告げる御長男の声がした。
苫小牧・山手町神召教会牧師(現・山手町教会)
大坂克典(召天)