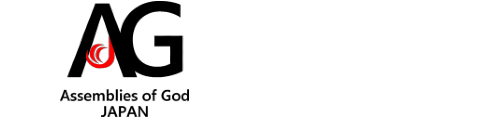『氷点』
~“罪とは、もう愛さないということ”
月刊アッセンブリーNews 第729号 2016/6/1発行より

人は時に「もう愛さない」という道を選ぶことがある。『氷点』冒頭、若い男との時間を楽しんでいたかった辻口夏枝は、母として子を愛するという使命を捨て、3 歳の娘ルリ子を外へ出した。ルリ子はその日殺される。誰かが「もう愛さない」という道を選ぶとき、愛に裏切られた者は淋(さび)しさという魔物に殺されるのだ。夫 啓造はこの妻を愛せなくなり、「もう愛さない」道 すなわち復讐を選ぶ。赤ちゃんが欲しいと言う妻に、娘を殺した犯人が遺した子をそれとは知らせずに与える。夏枝はその子を陽子と名づけ可愛がるが、その秘密を知ったとき愛せなくなってしまい、「もう愛さない」道 すなわちいじめることを選び、ついにはその出生の秘密を突きつけるに至る。
たぶん神が人間に求められる一番大事な使命は、愛することだ。愛すべきものとして与えられている存在を愛することだ。そうすれば幸せになれると神はご存知なのだ。しかし人は愛せなくなり、愛さなくなり、悲劇を繰り返す。その大元の原因は原罪だと三浦綾子こ は考えた。原罪とは神の方を向こうとしない人間の性質のことで、そこに根本的な ”的はずれ” があると三浦綾子は語る。愛の源である神に背を向けるとき、愛し愛されなければ生きていけない存在である人間は、壊れてしまう。
人は神の方を向かず自己中心に生きようとするくせに、愛されなければ生きてゆけない。そこで人は愛されるはずの価値を獲得しようとする。夏枝は美しさ、啓造は人格者であること、そして陽子は心が清いことをアイデンティティとした。でもそれらはやがて壊れ、渇きと絶望と、もう愛される何もない自分だけが残るのだ。
ゆるされる必要も愛される必要も自覚しない的外れの果てで、自分を愛せなくなり生きていられなくなった陽子の遺書が語る淋しさは、堀田綾子自身が敗戦後に体験したものだった。人生の目的も、生きていていいという確信も無くし、罪責感だけが残った魂の淋しさ。もう自分自身さえ愛せず凍えてしまう淋しさ、すなわち〈氷点〉を描きながら、三浦綾子はしかし、同時にそれを融かすものも指し示す。
「陽子」は綾子が13 才の時6 歳で夭折(ようせつ)した妹の名だった。医者の誤診で手遅れになった陽子は、「お姉ちゃん、陽子死ぬの?」と聞いた。姉は胸のつぶれる痛みを経験した。妹の死後、幽霊でもいいから会いたいと思った姉は、暗い所へ行っては「陽子ちゃん、出ておいで」と呼んだという。この愛惜がヒロインに「陽子」の名をつけさせた。三浦綾子の最愛の聖句は、ヨハネの福音書11 章35 節「イエスは涙を流された」だが、そこでイエスも「ラザロよ、出て来なさい」と呼んでいる。凍える絶望のなかで葬られている者に、いのちの希望の方に出ておいでと呼びかける声。それが三浦綾子の仕事であり、心だった。

《寄稿者》
森下辰衛 Tatsue Morishita
プロフィール
1962年岡山県生。元福岡女学院大学助教授。
全国三浦綾子読書会代表。 http://miura-ayako.com/
三浦綾子記念文学館特別研究員。