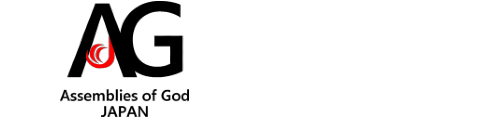あの闇の中に、もう神は来ておられた
~「道ありき」②
月刊アッセンブリーNews 第727号 2016/4/1発行より

1948年12月27日、旭川市十条11丁目にあった結核療養所白雲荘に入所していた綾子を一人の青年が訪ねて来た。前川 正28歳。17年前1年間隣に住んでいた幼馴染でクリスチヤン。前川は北大医学部の学生だったが、彼もまた結核に冒され休学中の身だった。彼は自分の命が多くは残されていないかも知れないと感じていたが、そんな頃幼馴染の綾子が結核なのに酒を飲みタバコを吸うという投げやりな療養態度でいることを聞き、訪ねて来たのだ。ところが綾子は前川に拒絶的な態度で接した。
「私クリスチャンなんて人種が一番嫌いなの。偽善者でしょ。私、死んだってクリスチャンなんかには絶対ならないから、帰ってちょうだい」
しかし前川はこの女の中に、「信じられる本物が欲しい、本物の愛があるなら欲しい。神なんて本当にいるのなら出て来て私を救ってみろ」と叫んでいる渇いた魂があるのを見逃さなかった。前川はその日から綾子に手紙を書き始めた。5年半後に死ぬまでに千数百通の手紙を書き、綾子も数百通書いて、計二千通余の手紙がやり取りされた。しかしその前川を振り払うようにして、翌年6月のはじめ、綾子はオホーツクの町斜里に出かけて行った。当時婚約していた西中一郎を訪ね、結納を返して婚約解消し、自殺しようと心に決めて。
婚約解消を切り出す綾子に、「結納金も、その10万円も綾ちゃんにあげるから、持って帰ってくれないか」と西中は言った。「3年も待っていたんだ」とも「月給をそっくりそのまま、一銭残らず、送った月もあるじゃないか」とも責めなかった。どんな気持ちで綾子が来たか、痛いほどに分かる人だった。西中家に泊まった深夜、綾子は一人で閣の中に出た。坂道を大股におりて行き、死ぬために海の中に入ったとき、綾子は肩をつかまれていた。それは西中一郎だった。彼は何も言わず背中を差し出した。
綾子は素直に背負われて「夜の海が見たかったの」と言った。彼は綾子を背負って砂山に登り、そこに一緒に腰をおろして「海ならここからでも見えるよ」と言って、真っ暗な見えない海を一緒に眺めてくれた。そして翌朝、彼は何も言わず斜里駅で手を振って別れてくれた。
『道ありき』には、この人に背負われた時「不意に、わたしの体から死神が離れたよう」だ、ったと書かれている。最も危険な暗い海で彼女を救った人。すべてを解って何も言わず涙をひとすじ流し、与えて与えて送り出してくれる人。あの人の背中に神さまがいた。前川 正の背後にいるかもしれない神に向かって求め叫んでいた私に対する答えは、あの時もう始まっていた。歩くこともできなくなった私を背負って歩いてくださる方がいた。「あなたが辛くて死んでしまいたい夜に、真っ暗な波の中で、私にはあなたを背負って歩く用意がある。私の背中に背負われなさい」と語りかけてくださる方が。そして絶望の砂の上に座って、見えない海を見ていた私の横に一緒に座ってくださっていた、あの方は誰だったのだろう?と『道ありき』の作家は考えている。そしてそれが誰であったか、分かって書いている。
血を吐くように叫び求める者に神は必ず答えて訪れてくださる方だということ。この求めと答えの体験を彼女は終生忘れなかった。だから、晩年の小説『母』でも、息子を殺され「神も仏もあるもんか!」と叫んだ母に「泣いてくださる方」として訪れてくださる主を書いている。

《寄稿者》
森下辰衛 Tatsue Morishita
プロフィール
1962年岡山県生。元福岡女学院大学助教授。
全国三浦綾子読書会代表。 http://miura-ayako.com/
三浦綾子記念文学館特別研究員。