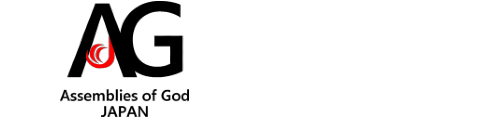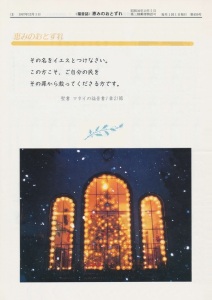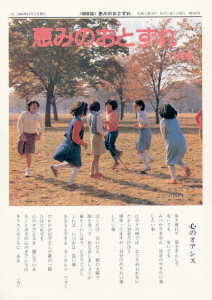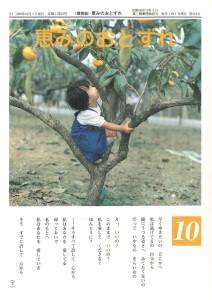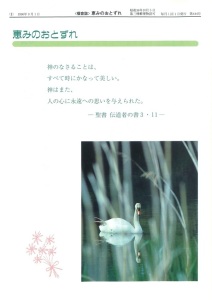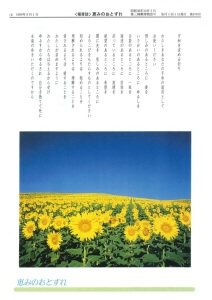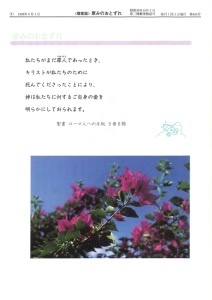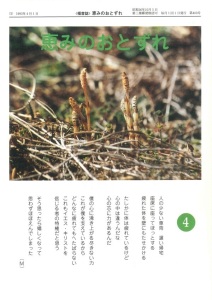vol.131- message 「素敵なChristmasをあなたに」
クリスマス!と聞くと、あなたの耳に何が聞こえ、あなたの目に何が見え、そして、あなたの心には何が思い浮かぶでしょうか?実は、この問いにあなたがどんな答を持っているかによって、今年のクリスマスが、あなたの将来、いや永遠に関する素敵なクリスマスになるかもしれません。
vol.130- message 「多いものが強いか」
私たちの住んでいる日本では、「多数決」によって何でも物事が決まります。小学校の学級会から国会まで、話し合いの最後は必ず多数決です。多数決とは、グループの中で最も賛同者の多い意見をそのグループの結論として決定する方法で、どんな小さな集団でもこの原理が絶対的な力を持っています。
vol.129- message 「“しあわせ”はあなたのとなり?」
“しあわせってなんだっけ、なんだっけ、ポン酢しょう油のあるウチさ……”。ひと時流行したコマーシャルソングです。ポン酢しょう油でしあわせになれるなら、こんな楽なことはないでしょう。最もギャグソングをそのまま信じてしまう心配もないとは思いますが、ただ、幸福を願うのは万人共通のことであることは確かです。
vol.128- message 「旅支度はできていますか」
私の姑は今年100才を越えた。若い頃は何でもよく覚えている人だった為か、現在の自分に耐えられないらしく「どうしてこんなに忘れっぽくなったの」と嘆く。眼はかすみ、歩くこともできなくなった日々、「老いる」ということはこれほどまでに苛酷なことかと思わされる。しかし又、この道は私も同じように通る道なのである。“老い”は人生の一部なのだ。
vol.127- message 「本当の平和をつくる者」
平和、それは人類共通、人類最大の願いです。私たち一人一人が、世界とまではいかなくとも、家庭で、身近な人間関係の中で、平和をつくり出す者となれたら、どんなにすばらしいでしょうか。ところが、そうなりたいと思っていても、なかなかそのとおりにはできないのが現実です。平和をつくり出すどころか、かえって日々「争い」をつくり出しているのが私たち人間の姿かもしれません。
vol.126- message 「生活を変える神の力」
まだフィリピンで宣教師をしていたころ、私は死刑囚として服役していたことがある牧師と、お付き合いをしていました。彼は6歳で路上生活を始め16歳で逮捕されるまで、考えつくあらゆる犯罪を犯し、殺した人間の数も思い出せないほどでした。・・・ところが、彼は46歳で刑務所を出て来たのです。そして現在は、こともあろうに牧師をしています。
vol.125- message 「愛せる者に」
ある人が庭造りをして、そこに芝生を植えました。ところが芝生が生えてくると、それと一緒にタンポポが生えてきました。タンポポを抜いても、あとからあとからタンポポが出てくるので困ってしまい、専門家に手紙を出しました。「どうしたらタンポポ退治ができますか?」しばらくして返事が来ました。「あなたは、タンポポを愛することを学んだらどうでしょう。」
vol.124- message 「行いではなく信仰により」
5月、それは春の日差しの力を受けて、新緑が誇らしげにその命を表現する時期です。私が住んでいる青森の八甲田山でも、雪の中から一斉に木々が若い緑の芽を出しています。しかし、その5月も人間にとっては、4月から新しくスタートした生活や、環境の中で最初に遭遇する試練、「5月危機」の時でもあるのです。
vol.123- message 「どういう人生を選びますか?」
日本の教育は世界的にも認められており、すばらしい人材を世に送り出してまいりました。しかし他の人との競争意識で動機づけられた教育は、いつも他の人を気にしてしまう人間を作り出し、一定のレベルに達した人は、エリート意識をもち、落ちこぼれた人は、劣等感をもってしまうことになります。
vol.122- message 「公平な愛の神様」
長い冬が過ぎ、暖かい春の季節となりました。また春は草木が芽を吹く生命の躍動を、感じる季節でもあります。聖書には「主は季節のために月を造られました。太陽はその沈むところを知っています。」と記されています。神は天と地を創造し、さらに季節もつくられ、私たちを愛しておられます。
vol.121- message 「まことの神・救い主」
「世界には多くの宗教があり、みな同じ所を目指しているのだから、どの宗教の神を拝んでもよいのではないか。何もキリスト教の神だけが正しくて、唯一の神であるとは言えないではないか」と、先日、一人の男性から質問されました。しかし、そこには誤解があります。
vol.120- message 「日々に新しく」
子供の頃の思い出の中に、正月はしかられず又掃除もしないでよかった事があります。大変うれしかったですね。では、私たちの生活もそれでいいのでしょうか。ところが聖書には「内なる人は日々新たにされています。」(Ⅱコリント4・16)と記されているのです。日々です。この一年のすべての日々、神様が新しくして下さっているのです。